103万円の壁、通称「年収の壁」。この制度が日本の労働市場や経済に与える影響は小さくありません。
しかし、時代の変化とともに、この壁を引き上げるべきという声が高まっています。なぜ103万円の壁を引き上げる必要があるのでしょうか?この記事では、その理由を7つの観点から詳しく解説します。少しずつ下がって確認ください。
この記事を読むと分かること:
- 103万円の壁とは何か、その問題点
- 103万円の壁を引き上げるべき7つの具体的な理由
- 各理由に基づいた具体的な引き上げ額の提案
- 壁の引き上げが経済や社会にもたらす影響
- 国民民主党:玉木氏の提案
- 今後の税制改革の展望
スポンサーリンク
103万円の壁とは?その問題点を解説
103万円の壁とは、年収がこの金額を超えると所得税が発生し、配偶者控除などが受けられなくなる制度です。1995年に設定されて以来、長年据え置かれてきました。この制度には以下のような問題点があります:
- 労働意欲の低下:多くの人が年収を抑えるために就業時間を調整
- 人手不足の助長:特に小売業などでパート労働者の確保が困難に
- 女性の社会進出の妨げ:キャリアアップや能力発揮の機会を制限
- 経済成長の阻害:労働力の有効活用ができず、経済活性化を妨げる
103万円の壁が女性の社会進出を阻害しているようにも見えますね。非常にもったいない
もちろん178万円が壁になったらそこにずれるだけと言えばそうなんですが凄く女性の働き方の幅が増えそう
もちろんセットで106万円130万円の社会保険料の壁も壊さないと意味がないhttps://t.co/JIUCQqYpoa https://t.co/b95t1bfNIQ pic.twitter.com/utTrFGaCNQ
— 地方選挙結果速報 (@senkyo_sokuhou) November 1, 2024
理由1:最低賃金の上昇に対応できていない
103万円の壁が設定された1995年から、最低賃金は大幅に上昇しています。
- 1995年の最低賃金(全国平均):611円
- 2024年の最低賃金(全国平均):1,055円
- 上昇率:約1.73倍
この上昇率を考慮すると、103万円の壁は約178万円に引き上げられるべきという計算になります。現状の103万円では、労働時間を大幅に制限せざるを得ず、労働力の有効活用を妨げています。
これらの理由から、最低賃金の上昇に対応するためには、103万円の壁を少なくとも178万円に引き上げる必要があります。
理由2:物価上昇と生活コストの増加
1995年以降、日本の物価は緩やかながら上昇を続けています。
- 1995年から2024年までの消費者物価指数の上昇率:約10%
- 特に近年は食料品や光熱費の価格上昇が顕著
物価上昇に対応するためにも、103万円の壁の引き上げは必要不可欠です。生活必需品の価格上昇に対応できる収入を確保することで、国民の生活の質を維持することができます。
理由3:実質所得の減少と生活水準の低下
過去30年間で、日本の家計は実質所得の減少に直面しています。
- 社会保険料の大幅増加:直近30年間で従業員負担率が1.5倍に
- 実質賃金の低下:1990年代初頭から2024年にかけて、実質賃金は約12%減少
- 可処分所得の減少:社会保険料の増加や消費税率の引き上げにより、手取り収入が減少
これらの要因により、103万円の実質的な価値は大きく目減りしています。
さらに理由2で述べた物価上昇と組み合わさることで生活水準の低下が加速しています。 物価上昇と実質所得減少の複合効果を考慮すると103万円の壁は大幅な引き上げが必要です。具体的には、以下の計算に基づいて引き上げ額を算出できます:
- 物価上昇率:約10%(1995年から2024年)
- 実質賃金の低下:約12%(1990年代初頭から2024年)
- 計算式:103万円 × 1.10(物価上昇分) ÷ 0.88(実質賃金低下分)
これらの要因を組み合わせると、103万円の壁は少なくとも128.75万円に引き上げる必要があります。
この引き上げにより、現在の経済状況に即した収入基準を設定し、労働者の生活水準を適切に維持することができます。
スポンサーリンク
理由4:憲法で保障された最低限度の生活水準を確保し、労働意欲を促進する
103万円の壁は、日本国憲法第25条で保障された「健康で文化的な最低限度の生活」を下回る可能性があり、憲法違反の疑いも指摘されています。
- 生活保護の平均支給額:単身世帯で月額約12万円、年間約144万円
- 都市部(1級地-1)の場合:単身世帯で月額約13〜14万円、年間156〜168万円
- 103万円の収入の場合:社会保険料等を考慮すると手取りは約90万円程度
生活保護費は憲法の理念に基づいて設定されています。103万円の壁がこれを下回ることは、憲法違反の可能性があり、労働意欲の低下や貧困の固定化につながります。
これらの理由から憲法で保障された最低限度の生活水準を確保するためには103万円の壁を少なくとも168万円(都市部の生活保護最高支給額)に引き上げる必要があります。
さらに、生活保護世帯には医療費無料などの追加的な支援があります。
これらの付加的な利益を考慮すると、就労意欲を維持し、働くことの経済的メリットを確保するためには、103万円の壁をさらに引き上げる必要があるかもしれません。 具体的には、以下の点を考慮して引き上げ額を再検討すべきです:
- 医療費の自己負担分(一般的な世帯で年間約12万円)
- 教育費支援(生活保護世帯の子どもへの就学援助)
- その他の付加的な支援(例:各種減免制度)
この修正により、生活保護世帯と就労世帯の間の実質的な差異をより正確に反映できます。また、「その他の付加的な支援」を加えることで、生活保護世帯が受けられる様々な支援の存在を示唆しつつ、具体的な金額化が難しい項目をカバーできます。
これらの追加的な支援を金銭的価値に換算し、103万円の壁の引き上げ額に反映させることで、より公平で、労働意欲を促進する制度設計が可能になります。
例えば、医療費の自己負担分だけを考慮しても引き上げ額は少なくとも180万円程度(168万円 + 12万円)になると考えられます(これでも各種補助を感がたら生活保護よりも下)。

理由5:女性の社会進出を促進する
103万円の壁は、特に既婚女性の就労に大きな影響を与えています。
- 女性の労働力参加率(25-54歳):1995年 66.5% → 2024年 80.5%
- 共働き世帯の割合:1995年 32.5% → 2024年 68.1%
壁を引き上げることで、より多くの女性が自身の能力を発揮し、キャリアを築く機会が増えます。これは個人の経済的自立だけでなく、企業の人材確保や経済の活性化にもつながります。
これらの理由から、女性の社会進出を促進するためには、103万円の壁を少なくとも150万円(現在の壁の約1.5倍、女性の労働力参加率の増加を考慮)に引き上げる必要があります。
理由6:人手不足問題の緩和につながる
日本の労働市場は深刻な人手不足に直面しています。
- 2024年の有効求人倍率:1.62倍(厚生労働省発表)
- 特に小売業、介護・福祉業界での人手不足が顕著
103万円の壁を引き上げることで、パートタイムやアルバイト労働者がより長時間働くことが可能になります。これにより、企業の人材確保が容易になり、人手不足問題の緩和につながります。
これらの理由から、人手不足問題の緩和につなげるためには、103万円の壁を少なくとも160万円(現在の壁の約1.6倍、有効求人倍率を考慮)に引き上げる必要があります。
理由7:経済の活性化と税収増加が期待できる
壁の引き上げは、以下のような経済効果をもたらすと予想されます:
- 個人消費の拡大:手取り収入の増加により消費が活性化
- 企業の生産性向上:人材確保が容易になり、業務効率が改善
- 税収の増加:長期的には所得税や消費税の増収が見込める
- 社会保障制度の持続可能性向上:保険料納付者の増加
短期的には減収になるかもしれませんが中長期で考えると減税が経済成長を促すことでそれらのデメリットは解消されていく可能性が高い。これらの効果は、日本経済全体の活性化につながり、持続可能な経済成長を支える重要な要素となります。
これらの理由から、経済の活性化と税収増加を促進するためには、103万円の壁を少なくとも170万円(生活保護最高支給額を上回る水準)に引き上げる必要があります。
103万円の壁を173万円にする案を国民民主が提唱
これらの事情を踏まえ、国民民主党が103万円の壁を178万円にすることを提唱しています。30年も基礎控除が変わらなかったのは異常であり国民の生活を無視して放置した政府の怠慢という意見になります。
国は税金を多く取り過ぎてきた。これが最優先の議題にならなかったので日本国民の生活は厳しくなる一方だったのです。
|
玉木雄一郎(国民民主党) ・103万円→178万円は、基礎控除を48万円→123万円にする話なので、学生アルバイトやパートさんだけでなく、すべての働く人の課税対象所得が減って減税の恩恵が広く及びます。(現在非課税で働いている人にとっては、非課税で働ける年収が最大178万円まで1.73倍増えます。) ・また、基礎控除は、憲法25条の「生存権」を保障するための制度で、生きるために最低限必要なコストを賄う所得からは税金を取らないという考えに基づいています。だからこそ、インフレによって生きるコストが上がるときには基礎控除の引き上げが必要なのです。ちなみに、1960年代は毎年、1970年代でも2〜3年に一度は、基礎控除の引き上げが実施されていました。 ・財源がないからできないとの主張がありますが、この問題は「財源論ではなく生存権の問題」なのです。財源があるから引き上げる、ないから見送るという話ではなく、インフレで生きるコストが上がっている以上、基礎控除の水準は引き上げなくてはならないのです。ちなみに1995年に現在の水準に引き上げたときには、特段の財源の手当てはしていません。 ・178万円の水準は高過ぎるとの声も聞きますが、これは、今日の最低賃金の水準を1995年と比較した場合、1.73倍になっていることから導かれた数字です。労働力の供給制約というサプライサイドの問題を解決することが、日本経済成長にとって不可欠であるとの観点からも、178万円の水準を強く主張しているところです。 ・いわゆる財源論の問題にあえて触れるとすれば、国の歳出・歳入をもう一度徹底的に見直すことを政府・与党には求めたいと思います。一昨年度、昨年度の2年の平均値で言うと、予算には計上したものの結局は使わずに残した予算が2年間の平均で年9.1兆円あります。逆に、税収は平均で年4.2兆円上振れして(想定より多く入ってきて)います。 ・使わない予算が9兆円、入ってくる税収は想定より4兆円も多いなら、計上すべき予算をもっと絞り込み、税収見積もりをより精緻にすれば、基礎控除の引き上げ分の減収など、いくらでも対応可能だと考えます。 ・また、手取りが増えれば、消費も活性化し、企業の売り上げも伸びて持続的な賃上げも可能になるでしょう。また、働き控えなど労働供給の制約が解消されれば、日本経済はもっと成長するでしょう。そうすれば、法人税も消費税も所得税ももっと伸びるでしょう。 ・計算上の単年度の減収にこだわってダイナミックな経済の動きを封じてしまうのは、まさにデフレ時代の発想ではないでしょうか。むしろ、基礎控除の引き上げこそが、デフレからの完全脱却の起爆剤になると強く信じています。 ・新しい経済政策で、皆さんの手取りを増やし、日本経済を元気にしていきましょう。応援、よろしくお願いします。 |
この意見に賛同する人も多く国民民主の支持率がアップしています。
(参考:世論調査政党支持率などまとめ)
実際に国民民主党が政府与党と折衝できるのは2024年の衆院選議席を増やしたからです。当然のことながらもっと議席が増えれば更に交渉力は上がります。
スポンサーリンク
減税を願う人が取るべき道
減税を願う人は国民民主に投票しましょう。そして周りの人にも伝えるといいでしょう。
現実には自民党、公明党、立憲民主党は国民民主党の案を批判しています。減税を願う人から見れば抵抗勢力になるのでおかしな意見だと思ったら批判するといいでしょう。
支持者の一部には「123万円までしか動いていない。国民民主の本気度が足りない」と批判している人もいますがおかしな話です。
123万円まで動いたのは国民民主の成果です。本来は更に動かすべきですが抵抗しているのが自民、公明、そして間接的には国民民主案を批判する立憲です。
批判すべきはそれらの政党であり減税を実現したいならば国民民主を応援し、周りの人にも伝え支持を広げることです。
批判して支持率が下がったら減税が遠のきます。叱咤激励はありですが過度な批判は慎むべきでしょう。批判ではなく国民民主を応援して支持を広げるべきです。
123万円以上にするなら以下のことが重要です。
- 国民民主(の減税案)を応援する
- 批判するのではなく叱咤激励にとどめる
- 批判すべきは増税側の自民、公明、立憲、その他国民民主案を批判する人達
- 知り合いにも伝え国民民主の支持率を上げる
追記:世論調査では103万円の壁見直し、7割の国民が評価
2024年12月の世論調査にてこの103万円の壁を動かすという案について質問がありました。およそ7割が評価しているという結果が出ています。それが直接、国民民主党への支持率アップに繋がっていると思われます。
- 103万円の壁を見直す動きについて68%が評価、7割近くが評価(日本テレビと読売新聞2024年12月世論調査)
- 「103万円の壁」見直し賛成74%(テレビ朝日2024年12月世論調査)
(その他参考:世論調査政党支持率まとめ)
まとめ:103万円の壁引き上げで、より働きやすく公平な社会へ
103万円の壁の引き上げは、現代の経済状況や社会構造に適合した改革といえます。
7つの理由から、壁の引き上げ額は約130万円から180万円までの幅がありますが最も高い水準レベルである国民民主案の178万円に引き上げることですべての課題に対応できると考えられます。
今後は、103万円の壁だけでなく社会保険の適用拡大や配偶者控除制度の見直しなど、包括的な税制・社会保障制度の改革が求められます。これらの改革を通じて、より多くの人が能力を発揮し、経済を活性化させる公平な社会の実現が期待されます。
この記事のまとめ:
- 103万円の壁を引き上げるべき7つの理由:最低賃金上昇、物価上昇、実質所得減少、憲法との整合性、女性の社会進出促進、人手不足緩和、経済活性化
- 各理由に基づく具体的な引き上げ額の提案:113万円〜178万円
- 最も高い水準である178万円への引き上げが、すべての課題に対応可能
- 壁の引き上げは、個人の就労機会拡大だけでなく、企業や経済全体にもプラスの影響をもたらす
- 今後は包括的な税制・社会保障制度の改革が必要
- より働きやすく公平な社会の実現に向けて、継続的な議論と改革が求められる
スポンサーリンク
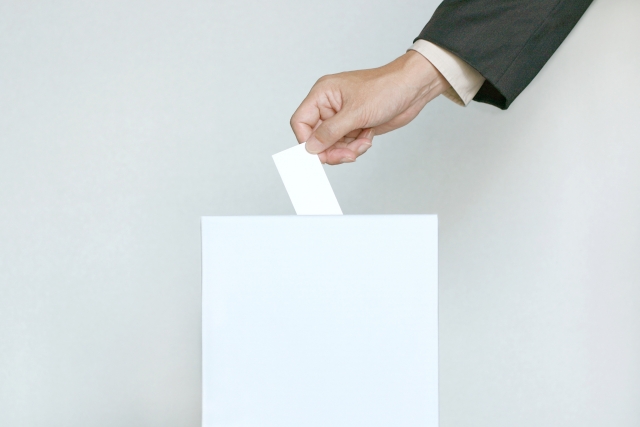
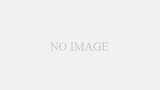
コメント