日本では社会保険制度の改革が議論されています。
特に日本維新の会が提案した改革案が注目されています。
この案では風邪薬や湿布などの一般的な医薬品を保険適用外とすることで保険料を削減することを目指しています。
具体的には、全体で4兆円の削減を目指し、平均で6万円の保険料軽減を提案しています。
この記事では日本維新の会の社会保険改革案の内容やそのメリット・デメリットについて詳しく説明します。
- 風邪薬や湿布などの保険適用外化の背景と目的
- 保険料削減の具体的な目標と方法
- 改革案のメリットとデメリット
- 医療費削減の根拠とその影響
スポンサーリンク
社会保険改革の背景
日本の社会保険制度は、医療費の増加や人口の高齢化に伴い、財政負担が増大しています。そして社会保険料は上がり続け働く現役世代の負担が大きくなっています。
更に少子高齢化が進んでいる状況なのでこのまま放置していたら社会保険料は更に上がり現役世代の負担は更に上がることになるでしょう。
それにより働き世代はお金の余裕がなくなり少子化が更に進み支える現役世代の減少で保険料負担が更に上がるという悪循環になっています。
このため、保険料の軽減や効率的な運営が求められています。日本維新の会の改革案は、このような状況下で提案されています。
風邪薬、湿布代などの適用外化の内容
日本維新の会の改革案では、風邪薬や湿布などの一般的な医薬品を保険適用外とすることが提案されています。いろいろと提言がありますがこの話が今回の医療費削減のメインと言えるでしょう。
(これは別に維新の新しい案というわけでもありません。もともと保険料提言のために与党でも提案されていた話です。もちろん今回維新が改革案として提案したことで改革がスピードアップする可能性がありそういった意味で注目したいところです)
これにより、保険料の負担を軽減し保険制度全体の効率化を図ることを目指しています。具体的には、全体で4兆円の削減を目指し平均で6万円の保険料軽減を提案しています。
スポンサーリンク
薬剤費の概算
2022年度の薬剤費のうち調剤費が約7兆9000億円と言われています。
このような薬剤費の削減が4兆円の保険料削減の根拠となっています。
当然のことながら高額な薬まで保険適用外にすることは現実的ではありません。比較的案かな薬を保険適用外にすることで4兆円規模の削減を目指すということです。
風邪薬や湿布代を適用外にするとどうなるか?
では具体的にどうなるのか?話を進めていきましょう。
現在は医者にかかった時にもらう薬代も保険適用となっています。例えば1000円の薬ならば保険適用の3割負担で300円で購入することができます。
今回の維新の案では風邪薬や湿布代など比較的負担が少ないものについては自己負担にするということになります。
すなわち今までは医者にかかることによって1000円の薬が300円で購入できましたが、維新の案の通りにするならば保険適用外になるので1000円の薬を定価そのままで購入することになります。
例として風邪薬、湿布代を挙げましたがそれ以外にも比較的安価な薬は全て保険の対象外にしようというのが維新の案です。それにより数兆円規模の削減を目指しているわけです(他の提案も合わせて4兆円規模)。
ほとんどの病気において(薬代が相当に高いケースは除いて)薬の3割負担適用が無くなると考えた方がいいでしょう。
メリットとデメリット
以下に維新案のメリット・デメリットをまとめます。
メリット
保険料削減
平均で年6万円の保険料軽減が期待できます。これにより加入者の負担が軽減されます(ただし与党や関連団体の抵抗があるでしょう。どこまで軽減されるかは不明)。
効率化
保険適用外とすることで、余分な計算などが減り保険制度全体の効率化が図られます。
無駄な医療の削減
今までは薬をもらう目的で医者にかかっていた人もおられました。そういった利用も減ることになり医療費削減に繋がると思われます。
デメリット
自己負担増加
風邪薬などの一般的な医薬品が保険適用外になるため加入者が自己負担する金額が増加します。それによって医療機関から足が遠のくことが予想されます。これまで病院に行くことで早期発見されていた病気の発見が遅れる可能性があります。
医療アクセスの低下
特に低所得層や高齢者にとって医薬品の購入が困難になる可能性があります。ここで低所得者や高齢者のための対策をすると結局は財源負担になるので今回の改革とは逆方向になります。
診療の減少による医療業界リスク
医療機関から足が遠のくことで診療が減少し医療機関や医師が経営難に陥る可能性があります。儲からない分野の医者が減る可能性もあり特定の医療が成り立たなくなる可能性も。また地域の医療空白地帯が増えるリスクが考えられます。
診療価格の上昇
先の診療のリスクに対して診療価格を上げて対応することも考えられますが、これは医療費を上げる方向であり今回の改革とは逆方向になります。また医者に行く側としてはダブルパンチでの自己負担増に繋がります。
製薬業界のリスク
薬の流通が減ることで製薬業界に影響を及ぼす可能性があります。負担を恐れた製薬会社が生産調整などをすることでストックが減り薬不足などの状況になる可能性もあるかもしれません。
影響と展望
維新の改革案は、医療費の増加や人口の高齢化に対する一つの解決策として注目されています。今後悪くなる一方なので早急な対策が必要なのは間違いありません。
しかし、その一方で今回の改革案では自己負担の増加や医療アクセスの低下、特定分野の医療の質や量の低下を懸念する声もあります。現実に医療機関から倒産が急増するのでは?という懸念の声が出ています。
維新の社会保障改革案の問題の1つですね。小児科、内科など儲からない医療分野が出てくる。特定分野の医療や地域の医療が崩壊する可能性がある
医療機関を救う方法としては診療費を上げるぐらいだろうが医療費は上がり改革とは逆方向に。本末転倒になる可能性もある https://t.co/kgV2YmrqlZ
— 地方選挙結果速報 (@senkyo_sokuhou) February 8, 2025
改革以前に医療現場は限界だという声もあります。改革が進んだら更に医療現場が苦しくなることでしょう。
病院の
赤字経営
大問題
診療報酬
もう限界…※解説
医療機関は儲かっていると思われがちですが、全然そんなことはなく、昨年の倒産は過去最多になりました。人件費や資材費が高騰する中で、市場原理が働かない(診療報酬)収益のなかでやりくりするのは、かなり限界を迎えている気がします。…— 内科医たけお☝ からだと心のクリニック院長 (@NaikaiTakeo) February 4, 2025
単純に改革するのではなく、医療制度全体の見直しや効率的な運営が求められます。
スポンサーリンク
まとめ
日本維新の会の社会保険改革案は、風邪薬などの保険適用外化を通じて保険料削減を目指しています。日本の社会保険はこのままでは成り立たないので日本維新の会の案は早急に検討、対応すべきと言えるでしょう。
ただ、この案には保険料の軽減や効率化のメリットがあり一方で、逆に自己負担の増加や医療アクセスが低下する可能性もあります。
さらに、診療の減少や最悪の場合には医療崩壊のリスクも考えられます。将来的には、医療制度全体の見直しが必要です。
- 社会保険制度の改革は、医療費の増加や人口の高齢化に対する解決策として重要
- 風邪薬などの保険適用外化は保険料削減を目指す一つの手段ですが、自己負担の増加や医療アクセスの低下を考慮する必要あり
- 診療の減少や医療崩壊のリスクも考慮する必要あり
スポンサーリンク
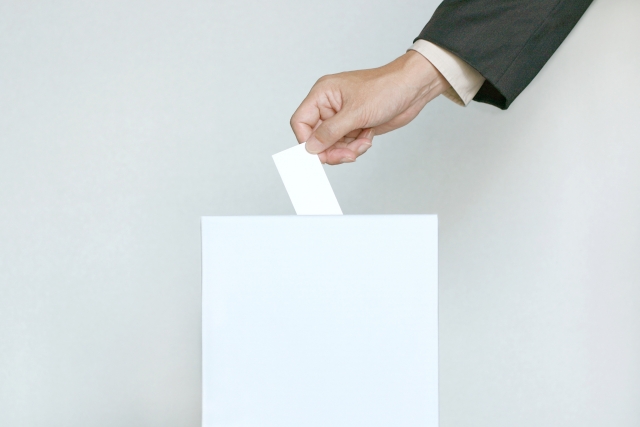
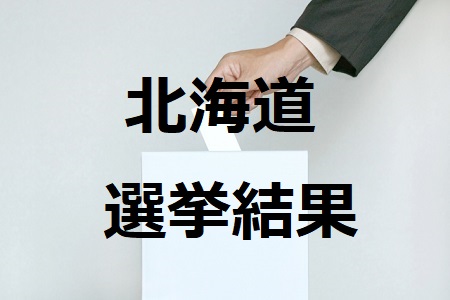
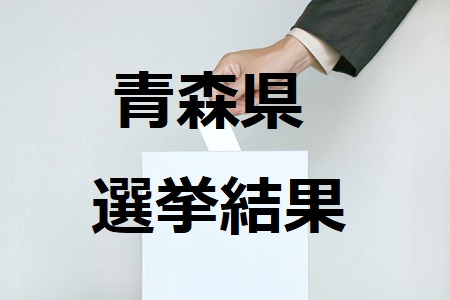
コメント